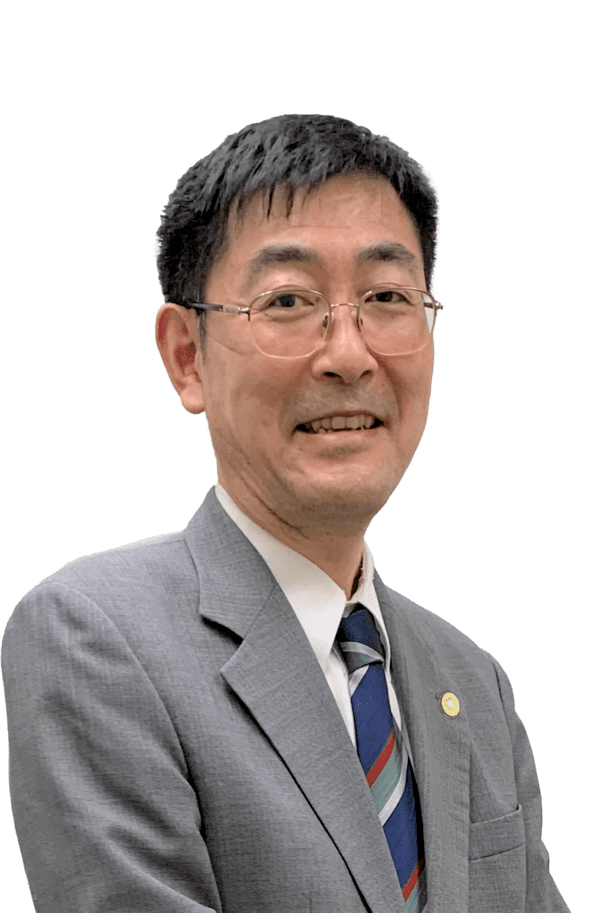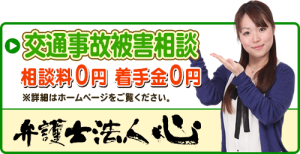頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害の認定について
1 はじめに
事故によるケガで最も多いケガが、頸椎捻挫・腰椎捻挫です。
そして、治療を継続したが、痛みが残った場合、痛みが残ったことを理由とする後遺障害の申請をすることになります。
しかし、実際のところ、なかなか認定されない傾向にあります。
2 画像検査での異常がないこと
頸椎捻挫・腰椎捻挫は、いずれも、レントゲンやMRIなどでの画像の異常は認められません。
痛みがあるが画像上の異常はないものが「捻挫」と診断されており、もし骨折や組織の断裂などがあれば、捻挫ではなく、〇〇骨折・〇〇断裂などの診断名がつきます。
画像検査の異常がないということは、痛みの原因が明らかにされていないことになるので、後遺障害の認定はされにくくなります。
3 症状の継続
後遺障害が認定されるためには、症状固定、即ち治療終了後も痛み・関節の可動域制限、傷跡などの症状が継続することが要件となります。
症状が継続せず、治ってしまうのであれば、当然のことながら、後遺障害には当たらないためです。
後遺障害の原因が、関節の変形や傷跡など、目に見えるものであれば、症状の継続の有無は比較的判断しやすいと思います。
しかし、痛みは目に見えませんし、先ほどお伝えしたとおり、痛みの原因とされる捻挫も、検査画像での異常が認められない場合に付く診断名です。
では、「痛みの継続」について、どのように判断するかというと、事故の大きさ(車両の損壊の程度など)、治療期間、通院日数、被害者の年齢、治療経過など様々な要素を考慮して判断していくことになります。
4 認定されにくい理由について
一般的な傾向として、車両どうしの事故において車両の損傷が軽微であること(→身体への負荷が小さいと考えられる)、通院回数が少ないこと(→症状が軽いとみられる)、若年であること(→回復力が強いと考えられている)、症状の経過の中に「症状の改善」についての記載があること(→いずれ治癒に向かうと考えられる)は、いずれも、認定されにくい要素となります。
後遺障害が認定されなかった場合に、これに対する異議申立てをしたが、それでも後遺障害が認められなかったケースでは、診療録などに症状の改善についての記載があることが、認定されない理由とされることが多いように思われます。
また、「痛みの継続」は多分に「将来の予測」ということになるので、このことが,認定されにくかったり、認定される事案と認定されない事案との区別がつきにくい理由と思われます。
4 おわりに
後遺障害の認定は、事案によっては難しい問題が生じることがありますので、専門家である弁護士にご相談ください。